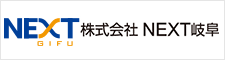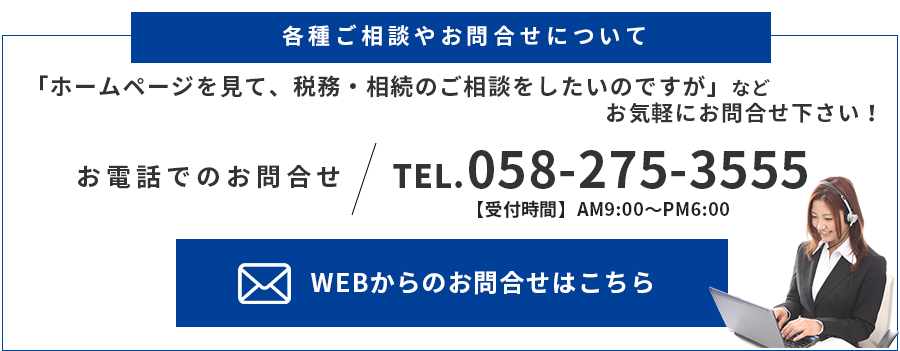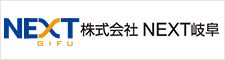財産をもらったり、個人の収入など身近な相続税
<下記におけるすべての記述は、平成30年4月末現在施行されている法律に基づいておりますが、実際の適用につきましては、必ず税務署や税理士にお問い合わせ下さい。>
相続税とは
私たちのまわりにはいろいろな税金があります。所得にかかる所得税や、消費にかかる消費税などが代表的なものですが、財産にかかる税金の一つが相続税です。
相続税は亡くなった人の財産を受け継いだ時、その「財産」に応じてかかる税金です。キチンと所得税を支払った残りを蓄えた財産になぜ相続税がかかるのかといえば、多額の財産を相続し、働かずに暮らせるのでは他の働く人に対して不平等なので、「死亡」を機会に相続税をかけ広く国民に分配しようとする「富の再分配」という考え方によるものです。次に、どれくらいの財産があると、相続税がかかるのかといえば、亡くなった人の財産が次の公式(基礎控除額)によって計算された金額よりも少ない時は、相続税はかかりませんし、当然申告する必要もありません。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この基礎控除額を超える財産がある場合に超えた財産金額に対して相続税を計算することになります。法定相続人は民法に定められており、相続税の計算では、財産を受け継いだ人数に関係なく、法定相続人そのものの人数が、計算基準になります。
なお、養子が複数の場合には、実子がいるときは1人だけ、いないときでも2人までしか、法定相続人の数に含めません。
法定相続人と相続順位
相続は一方的な財産の移動ですから、誰がもらえるのかを法律的にはっきりさせておかないとトラブルのもとになります。民法では財産を相続する人の範囲を被相続人から見た次の人と定めています。
① 配偶者・・・・・・夫または妻
② 子供・・・・・・・・子供が先に死亡している場合は、その子供である孫(直系卑属)
③ 親・・・・・・・・・・親が死亡し祖父母がいる場合は、祖父母(直系尊属)
④ 兄弟姉妹
ただし、これらの人がすべての相続人になるのではありません。一定の順序に従って相続人になる人及びその人が相続権を主張できる財産の取得割合(法定相続分)を次のように定めています。
(相続順位と法定相続分)
| 順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子供(直系卑属)(注1) 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 第2順位 | 親(直系尊属) 1/3 | 配偶者 2/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 配偶者 3/4 |
(注1)実子のほか、法律上の子、すなわち養子も含まれます。養子にできるのはアカの他人に限りません。例えば、自分の孫や甥、姪を養子にすることもできます。ただし、相続税は相続人の数が多いほど少なくなるため、明らかに相続税減らしのための養子縁組を防ぐために、実子がいる場合は養子一人、実子がいない場合は養子二人までを相続人の数に含め計算します。
税率表
相続税の税率は、各相続人が取得する財産の評価額が高くなればなるほど高くなり、その税率は次の通りです。
| 法定相続分に応ずる各取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超3,000万円以下の部分 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下の部分 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下の部分 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下の部分 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下の部分 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超の部分 | 55% | 7,200万円 |
相続税=A×B-C(上記の表を使って計算します。)
ただし相続税は、遺産の評価額から遺産に係る基礎控除の金額を控除して計算します。
次に、相続税は遺産の額が同じであっても、次表のように、法定相続人の数が多いほど税金は少なくなります。
また、法定相続人の中に配偶者がいれば、配偶者が取得した財産については、ほとんど税金がかからない特例があります。
相続税額の早見表
| 遺産額 (基礎控除額控除前) |
配偶者と子が相続人の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子供1人 | 配偶者+子供2人 | 配偶者+子供3人 | 配偶者+子供4人 | |
| 5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 0 |
| 7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 50 |
| 8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 100 |
| 9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 163 |
| 1億円 | 385 | 315 | 262 | 225 |
| 1.億円 | 920 | 747 | 665 | 587 |
| 2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 |
| 2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,687 |
| 3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
| 5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 |
| 10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 |
注1.上記の法定相続人は、配偶者と実子を想定したものであり、法定相続人の内、一親等以外の者(養子縁組した孫等)がいた場合、その相続人の相続財産に対する相続税額は2割増しとなり、上記の相続税額が変わります。
注2.上記相続税額は、配偶者が何も遺産を相続しない場合の税額である。
注3.配偶者が、遺産額の2分の1又は1億6千万円のいずれか多い遺産額を相続した場合は、上記相続税額は、配偶者の税額軽減により遺産総額が3億2千万円以上の場合で2分の1となります。
注4.上記相続税額は、平成30年4月1日現在の法律に基づく税額である。
Q4.相続税の負担を軽くするにはどうしたらよいのですか?
A.相続税を安くするための対策として、4つあげることができます。
①養子縁組をする
法定相続人を増やすことにより基礎控除額を増加させ、累進課税の適用部分を低くすることができます。ただし、養子にも当然相続権が生じますので後にトラブルにならないよう適任の人でなければ意味がありません。
②生前贈与(本人の財産そのものを事前に贈与により減少させてしまう)
贈与することで財産をなくすといっても、贈与には相続税よりも割高な贈与税が待っています。
ですから、贈与税も安くすることを考えながら、計画的に贈与することが必要です。贈与により贈与税を支払っても、相続税より安ければよいことになります。贈与税は、一人1年(暦年)につき110万円の基礎控除と、贈与財産の価額に応じて税率が異なる累進課税を採用しています。
よって、1回で贈与するか何回(何年)かに分けて贈与するかによって、下記の表のように税額は大きく違います。
1,000万円を贈与した場合の贈与税額の試算 「一般贈与財産」の場合
| 贈与を受ける人 | 1回(1年) 税額計 |
5回(5年) ※1年毎に200万円 税額計 |
|---|---|---|
| 1人 | 2,310千円 | 90千円 |
| 2人(均等) | 1,060千円 | 0 |
| 3人(均等) | 705千円 | 0 |
このように、生前贈与は贈与の「回数」と「人数」を上手に組み合わせることがポイントとなります。
しかし、毎年継続して、かつ贈与金額が同額である場合は、連年贈与とみなされ、毎年の贈与金額の合計が本来の贈与金額とされる可能性がありますので、同額の贈与はお薦めできません。
また、生前贈与は贈与した行為が単なる形式上ではなく、実態として行われている事が必要となります。ただし、贈与税は相続税の前払い的な性格を持っていますから、贈与することによって納税時期が早まってきます。
つまり、贈与してもらった翌年3月15日までに、申告及び納税が必要ですから、そのことによる金利面も頭に入れておいて下さい。
③相続財産の内容を変える(財産の評価を低くしてしまう)
相続税を計算するとき、財産を評価します。評価が安ければ相続税も当然安くなるわけです。
一般的には、相続財産に占める割合の第1位にあげられるのが土地です。土地の評価を下げるには次のような方法があります。
(1)遊休地にはアパートを建てて土地と建物の評価を下げる
遊休地があれば、アパートを建築し賃貸すれば、アパートの敷地は、貸家建付地となり、更地価額に対して、(借地権割合×借家権割合)の分だけ評価減になります。
普通住宅地区では借地権割合が50%、借家権割合が30%のケースが多いので、通常15%の評価減となります。また、家屋(アパート)についても借家権割合30%を評価減できます。(但し、アパートに空室がある場合は貸付割合に応じて、敷地及び建物の評価減を行います)
ところで、相続税を安くする目的でアパートを建てても、入居者がなくてはアパート経営が成り立ちません。万一、入居者が一人もなければ貸付割合がゼロとなり、敷地も建物も評価減は全くされませんし、建築費を借入で賄ったとすれば返済も出来なくなります。立地条件、周りの環境、交通の便、入居者のニーズ、家賃相場等、十分検討して判断する必要があると考えます。
④納税資金の準備(節税を意識しながら、税金の準備をしておく)
500万円×法定相続人の数=非課税枠(生命保険金だけでなく、死亡退職金にも別枠である)
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までは課税されません。この場合、1,500万円は相続人全体に認められたことですから、相続人のうち貰えない人があっても1,500万円までの金額が非課税なのです。相続人の一人が1,500万円全てをもらったとしても非課税なわけです。
ただし、この非課税枠が使えるのは、相続人だけですので、相続人でない人が生命保険金などをもらったときには、全額に対して相続税がかかります。いずれにしても、非課税限度額までは生命保険に加入していた方が、遺産を現金で残すより節税となります。この方法は是非お薦めしたいのですが、加入契約の形態に注意して下さい。
生命保険契約の形態によって税金も変わる
| 保険金の種類 | 番号 | 保険受取人被保険者 | 契約者 | 契約者の相続人 | 第三者 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 死亡保険金 | ① | 契約者 | 相続税 | 相続税 | 相続税 |
| ② | 契約者以外 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 | |
| 生命保険金 | ③ | 契約者 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 |
| ④ | 契約者以外 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 |
★一時所得の計算方法
・保険金額-必要経費(払込保険料)-50万円(控除額)=一時所得×1/2=所得税課税対象額
・契約形態で一般的なのは上記①のAのケースと考えられますが、相続財産が大きい場合は、②のAの方が有利になる場合があります。
相続税のよくあるご質問
相続税に関するよくあるご質問や、実際にお問い合わせ頂いた事例と返答を紹介いたします。
贈与税とは
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に受けた個人に対してかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。
贈与税は、次の算式で計算されます。
( a - 基礎控除額(110万円) ) × 税率 = 税額
(注) a ・・・ 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格合計
つまり、年間110万円までの贈与については贈与税がかからないことになります。
贈与税の税率は、贈与を受けた財産の評価額が高くなればなるほど高くなり、その税率は次の通りです。
現在、税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。相続税と比較すると明らかに高い税率となっています。
①一般贈与財産用(一般税率)
この表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税計算に使用します。
例えば、兄弟間・夫婦間贈与、親から子への贈与で子がまだ未成年の場合などが該当します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 10% | – |
| 200万円超300万円以下の部分 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下の部分 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下の部分 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下の部分 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下の部分 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下の部分 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超の部分 | 55% | 400万円 |
②特例贈与財産用(特例税率)
この表は、直系尊属(祖父母・父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫等)への贈与計算に使用します。
| 基礎控除(贈与税の配偶者控除)後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
①相続時精算課税
一定の要件を満たした場合に、贈与に対する贈与税を相続時に精算する課税制度です。この制度は、贈与時の財産の価額から控除する金額として2,500万円(累積限度額)の特別控除があります。
【制度の概要】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
②住宅取得等資金の贈与税の非課税
【制度の概要】
直系尊属(父母、祖父母など自分より前の世代で血縁関係のある親)から住宅取得のための資金の贈与を受けた20歳位上の方が適用を受けることが可能です。住宅用家屋の契約日に応じて、下記金額を贈与財産の価額から控除することが可能です。
【非課税金額】
| 住宅用家屋の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 平成28年1月1日~令和2年3月31日 (消費税10%以外での契約であること) |
1,200万円 | 700万円 |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 (消費税10%での契約であること) |
3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日~令和5年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
贈与税のよくあるご質問
贈与税・相続税に関するよくあるご質問や、実際にお問い合わせ頂いた事例と返答を紹介いたします。